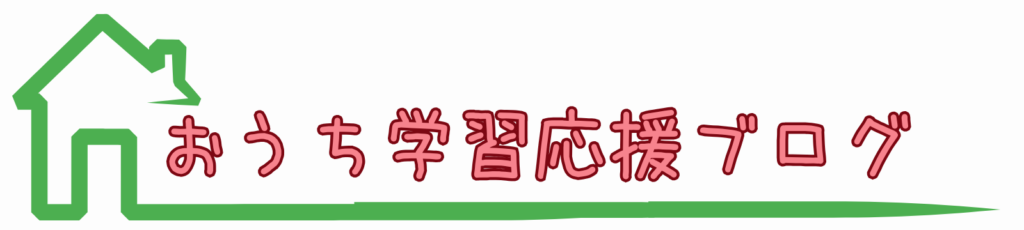塾なしで勉強させたいけど、家庭学習は続けられるか不安…
そう思っていませんか?
- 「家庭学習の習慣をつけようと思ったけど、なかなか続かない…」
- 「子どもが勉強を嫌がって、親のほうがイライラする…」
- 「塾に行かせなくても、本当に学力は伸びるの?」
- 「でも、塾に通わせるとお金がかかるし…」
実は、これ… 私もまったく同じことを思っていました。
とはいえ、塾に通わせるとなると、年間50万円以上の費用がかかることも。
「家庭学習でいけるなら、それが一番いい。でも、子どもが勉強しない子になったらどうしよう…?」
そんな迷いがありました。
でも、ある方法を実践したことで、
この記事では、そんな「塾なしでも、無理なく学習習慣をつける方法」をお伝えします。



「家庭学習をどう進めたらいいか分からない…」そんな方こそ、ぜひ最後まで読んでください!
教育費について気になる方はこちらの記事を参考にしてみてください。
塾なしでも教育費はかかる…!家庭学習派ママの「リアルな備え方」
塾なし家庭学習の進め方(成功のコツ)
「家庭学習を頑張ろう!」と決めたものの、
- 勉強時間を決めても、すぐにダラダラしてしまう…
- 親が隣にいないと、すぐに遊びたがる…
- 「あとでやる」と言って、結局やらない…
- 宿題で精一杯。プラスの勉強なんて無理!
という状況に陥っていませんか?



やらせようとすればするほど、疲れちゃう・・・



子どもってなかなか思うように動いてくれないですよね。
家庭学習を続けるには、親も疲れないようにサポートすることが大切です。
そんな、親も疲れないようなサポート術を、
- 学習スケジュールの決め方
- 子供のやる気を引き出して習慣化する方法
の2つに分けて説明していきます。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ、参考にしてくださいね。
子どもが自分から勉強するスケジュールの立て方
「毎日○時から勉強しよう!」と決めたのに、気づけば漫画を読んでいたり、遊んでいたり…。
「時間を決めるだけでは、子どもは動かない」のが現実ですよね。
こうした悩みは、スケジュールの決め方を工夫すれば解決できることが多いです。
①「時間」ではなく「行動」で決める
勉強する時間を決めたいときは、行動とセットにしましょう。
そうすることで、生活リズムの中に学習時間を自然と組み込むことができます。
我が家の長女は、
朝起きて支度をする⇒勉強タイム⇒朝ご飯⇒歯みがき⇒読書⇒登校
という朝の流れを作り、実践しています。ルーティーンになっているので、「勉強しなさい」と言わなくても取りかかれています。
- いつ勉強するかは、お子さんが決めるようにしましょう。親に決められてしまうと、子どもはやる気になれないことが多いです。
- 1日の生活時間の中で、いつなら勉強に取り組む気持ちになれそうか、お子さんに考えさせてみましょう。
②1日の学習時間の目安を決める
1日の中でいつやるのか決まったら、学習時間を決めましょう。
1日の学習時間の目安は、
学年×10+10分
で、考えてみてください。
小1:20分
小2:30分
小3:40分
小4:50分
小5:60分
小6:70分
小学校では、宿題の時間を含めてこれくらいの家庭学習が望ましいと言われています。
ただ、受験を考えているといった場合は、さらに受験のための勉強時間が必要になってきます。
長すぎると続かないので細切れにして、トータルの時間が上記の時間になるようにしてもOKです。
例えば、小学3年生のお子さんなら
朝食前10分(ドリル)
おやつの後20分(宿題)
寝る前10分(ドリル)
といったようなリズムにするのもありです。
我が家の長女の場合は、
朝食前20分~30分(進研ゼミ)
夕食後テレビを見てから30分(宿題+読書)
といった感じで家庭学習に取り組めています。



細切れでいいなら、うちの子でもできそう!



子どもの集中力は短いです。集中力が切れたのにダラダラやらせても効果はないので、短め×毎日がポイントですよ。
③週単位または月単位で学習計画を立てる
1日の中でいつどれくらい勉強できそうか決めたら、次は週単位や月単位での学習計画を立てていきます。
学習計画を立てて勉強を見える化することで、やるべきことが明確になります。
できたらシールやご褒美ハンコなどでチェックできると達成感も味わえるので、おすすめです。
1・2年生の学習計画の立て方
低学年のうちは、あまり細かすぎる計画を立てるのはおすすめしません。
カツカツの予定を組んでしまうと、勉強=つらいものになってしまう可能性があるからです。
例えば、お子さんの好きなキャラクターのドリルを一緒に選んだら、1回1ページやろう、と決めます。
「毎日必ずやる」というルールは作らず、「ドリルを終わらせる」というゴールだけ設定。
これくらいの計画でOKです。



1・2年生ではまず、家でも勉強することを当たり前にしていきましょう。
3・4年生の学習計画の立て方
3年生になると、理科・社会・外国語活動が増え、宿題も難しくなってきます。
中には、宿題だけで1時間かかってしまうような子どももいます。
そのため、宿題以外の家庭学習は、無理のない範囲で決めていきましょう。
- つまずきが見られる子どもは、克服することを目標に、苦手な部分だけ
- 基礎を固めるために算数の計算問題と漢字だけ
- 国語の読み取りや、算数の難問など、応用問題に取り組む
といったように、子どもの学力に合った勉強を選ぶことが大切。
3・4年生では、できるだけ毎日取り組めるように、学習カレンダーを作るのがおすすめです。



3・4年生では、「どの教科の何に取り組むか」を子どもと一緒に考えてみましょう。
5・6年生の学習計画の立て方
高学年では、自分で計画を立ててやり切ることが目標。
いつ何をやるのか、自分で決めて取り組めるようにします。
例えば、
- 月曜に「1週間のやることリスト」を作る
- 土日は復習+予備日にする(できなかった日の穴埋め)
といったように、具体的な計画を立てます。
できなかった日の穴埋めもできるようにして、最後までやり切れるようにすることが大切です。



5年生になったら、自分で計画を立てて、その通りに進められるようになるの?
急にはできるようになりません。計画は立てられても、計画通りにいかないということが多いと思います。
そんな時は、
- 「1日分の量が多かったかな?」
- 「勉強する時間を変えてみる?」
と、どうしたら計画通りに進められるかを考え直しましょう。
そうすることで、計画を立てる力、調整する力が育ちます。



5・6年生では、自分で計画を立てる経験をたくさんさせてあげましょう。そして、うまくいかなかったら調整するのを、手伝ってあげましょう。
家庭学習を習慣化する!やる気アップの工夫
- 学習計画を立てて家庭学習を始めたものの、「後でやる」
- 最初はやる気満々だったのに、「今日はいいや」と言い始める
こうして、家庭学習が続かなくなってしまうのはよくある話です。
家庭学習を継続させるために、習慣化するための工夫は欠かせません。
小さなゴールとご褒美を作る
「できた」を見える化して、達成感を味わえるような仕組みを作りましょう。
子どもにとって成功体験は、次も頑張ろうという大きな原動力になります。
だから、市販のドリルにはよくご褒美シールがついているんですね。
家庭学習に取り組むときは、
- 1日分の学習ができたら
- 1ページできたら
といったように、ゴールを決めて、ご褒美シールやハンコをもらえるという仕組みを作るのが効果的です。



大きなゴールだと挫折しやすいので、なるべく小さなゴールにするのがおすすめです。
さらに、
- シール10こたまったら、特別なキラキラシールがもらえる
- シールが30こたまったら、好きな本が買える
といった、区切りごとのゴールを作るのもおすすめです。
子どもが好きそうなご褒美を一緒に決めて、「がんばりたい」という気持ちを引き出しましょう。
ポジティブな声かけをする
- 「×ばっかりでぜんぜん合ってない。ちゃんと問題を読みなさい」
- 「簡単な問題で間違ってる。こんな問題も分からないの?」
- 「やるって言ったのにやってない。いつになったらちゃんとやるの?」
こんな声かけはアウトです。
たとえ現実がそうだとしても、そう言ってしまっては、子どものやる気はなくなる一方です。
なかなかできない子どもにイライラしてしまう気持ちも分かりますが、ぐっとこらえましょう。
「ちゃんと取り組めたね。この問題で間違っちゃったのは悔しいね」
と共感しつつ、取り組めたことに対しては褒めてあげましょう。
もしかしたら子どもの反応は薄いかもしれませんが、こうした声かけをすることで、自分のことを分かってくれているという信頼関係にもつながります。
そして、
- 「今日は前よりも早く計算ができたね」
- 「この問題、ちゃんと考えて解けたね」
- 「2日連続で取り組めてすごい」
と、少しの成長も見逃さずに褒めてあげましょう。
親のサポートを最小限にしたいときは「通信教育」もあり



サポート方法は分かったけど、やる気を継続させるのってやっぱり大変そう・・・うちの子に学習計画なんて立てられないかも。
子どもにつきっきりでサポートできるわけではないし、これだけのサポートをするのは、ちょっと骨が折れますよね。
そんなときは、通信教育に頼るのもありです。
たとえば、我が家が使っている「進研ゼミ」なら、子どもが自分で学習を進められる工夫がたくさん。
- その日の学習をAIが提案
- がんばりポイントでご褒美がもらえる
- 間違えても「ここが惜しかったね!」とポジティブに励ましてくれる
進研ゼミについては、こちらの記事をぜひ参考にしてくださいね。
成功する家庭学習の環境作り
家庭学習を成功させるには、環境も大切です。
勉強する場所を作る
お子さんの勉強スペースはありますか?
おすすめはリビングですが、大切なのは、いつも同じ場所で勉強できるようにしておくこと。
勉強する場所を決めておけば、「ここに座ったら勉強する」という意識に自然と変わることができます。
そして、勉強スペースには、鉛筆や消しゴムがすぐに取れるように用意し、取り組むドリルやワークを置いておきます。



座ったらすぐに取り組める環境にしておくことがポイントです。
親も一緒に勉強する
子どもが勉強するときは、親も一緒に勉強の時間にするとさらに効果的です。読書でもいいです。
家よりも図書館の方の方が勉強できるという経験はありませんか?
周りの人が静かに勉強や読書をしていると、自分もやろうというスイッチが入りますよね。
そういう環境をおうちで作ってあげることにより、子どもも勉強に集中できるようになります。
まとめ|家庭学習を続けるコツは「がんばりすぎないこと」
- 「家庭学習って大変そう」
- 「続けられるか心配」
そんな不安は、私も何度も感じました。
でも、
毎日少しずつ・無理なく・楽しく。
この3つを意識すれば、塾に通わなくても、子どもはちゃんと力をつけていきます。
家庭学習で大切なのは、勉強そのものよりも「習慣化」すること。
1日10分からでもいいんです。
「やらなきゃ」ではなく「やってみよう」と思える工夫を、少しずつ生活に取り入れていきましょう。
我が家もまだまだ試行錯誤の連続ですが、今では子どもたちが自分のペースで学ぶ力が少しずつ付いてきたと感じています。
そしてなにより、親子で学びの時間を共有できるのは、家庭学習ならではの大きな魅力です。
塾なしで家庭学習がやっていけるか不安な方に、この記事が少しでも役に立ったら嬉しいです。