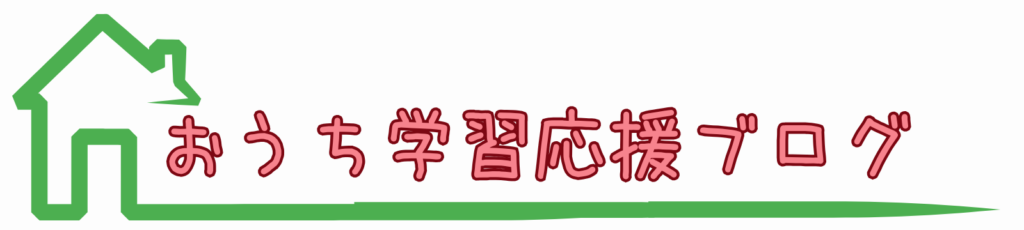「塾に行かせないなんて、うちの子だけ…?」と悩んだ日々
心のどこかで、そう感じていました。
こんにちは。「おうち学習応援ブログ」を運営しているきみどりです。
元小学校教員で、現在は中学校の非常勤講師。3人の子どもを育てている母です。
長女が小学校3年生になった頃、少しずつ周りの子たちが塾に通い始めました。
「うちもそろそろ…?」という空気に、心がザワザワし始めたのを覚えています。
教員としての経験、母としての葛藤
実は私自身、教員時代によくこんな相談を受けていました。
「先生、塾に行かせた方がいいでしょうか?」
「通信教育だけじゃ不安で…」
そのたびに、「おうちでもちゃんと学べますよ」と伝えてきました。
でも、いざ自分がその立場になってみると――
「塾に行かせなくても本当に大丈夫かな?」
と、不安に。
でも――
「塾に行かせるとなると、家計的に厳しい。」
「下の子たちの習い事や学用品だって、これからもっとかかる。」
それでも私は思いました。
子どもには、“ちゃんとした学び”をさせてあげたい。
進研ゼミを“使いこなす”工夫を始めてみた
実は、我が家では長女が年長の頃から**進研ゼミ(チャレンジタッチ)**を使っていました。
ただ、当時は「とりあえずやってる」くらいの感じで、しっかり活用できているかというと、自信はありませんでした。
だからこそ、3年生のタイミングで周りの塾通いが増えてきたとき、心が揺れたんです。
「やっぱり塾に行かせた方がいいのかな……」
「進研ゼミだけじゃ、不十分なんじゃないかな……」
でも、塾に通わせるには家計的なハードルも高いし、何より、
「せっかく続けてきた進研ゼミを、ちゃんと活かせていないんじゃないか?」
そんな想いが、ふと心に浮かびました。
それなら、まずは“今ある教材を最大限に活かしてみよう”と決めて、少しずつ取り組み方を見直すことにしたんです。
子どもに起きた小さな変化が、大きな自信に
とはいえ、「最大限活用する」って、最初は何から始めたらいいのか分かりませんでした。
でも、ひとつひとつ工夫していくうちに、少しずつ見えてきたんです。
たとえば――
- 「今日はどこをやるか」を一緒に決めたり
- できたところに○をつけて「よく頑張ったね!」と声をかけたり
- ときには間違えた問題を一緒に考え直してみたり
そんなふうに、「進研ゼミをただやらせる」のではなく、“一緒に向き合って、使いこなす”ことを意識するようにしました。
すると、だんだんと変化が見えてきたんです。
「今日はもうやったよ」
「この問題、簡単だった!」
「もっとやっていい?」
そんな声が、娘の口から自然と出てくるようになりました。
もちろん、毎日うまくいくわけじゃないし、やる気が出ない日や、ぶつかる日だってあります。
でも、あのとき「塾じゃなくてもやれるかも」と信じて動き出したことで、“家庭でも、子どもはちゃんと育つ”という実感が少しずつ育っていきました。
家庭でも、子どもの学力はちゃんと育つ
進研ゼミを始めて6年。
高学年になった長女は今、学校で成績トップクラスを維持。
進研ゼミは、計画を立てて自分から取り組む習慣がしっかり根づいています。
学校の学習にも意欲的で――
「算数の問題、難しかったけど、ちゃんと分かったし、手を挙げて答えられたよ」
「理科のテスト、また100点だった!」
そんな姿からも、学校生活を楽しみながら前向きに過ごしていることが伝わってきます。
このブログを始めた理由
こうした日々の積み重ねを通して、私はあらためて気づいたんです。
「塾に行かなくても、子どもの学びは家庭でも育てられる」
「家計にやさしいやり方でも、子どもはしっかり力をつけていける」
もちろん、何もせずにうまくいったわけではありません。
たくさん悩んで、試行錯誤して、親子で向き合いながらやってきたからこそ、今があります。
だからこそ私は、
- 塾に通わせてあげたいけど、家計的に厳しい
- 通信教育だけで大丈夫か不安
- 何から始めたらいいのかわからない
そんな風に悩むママ・パパたちに向けて、
自分の経験と知識を“役立つカタチ”で届けたいと思うようになりました。
それが、このブログを始めたきっかけです。
このブログで発信していること
このブログでは、
- ✅ 進研ゼミを活用した、塾なしでも成績を伸ばす家庭学習法
- ✅ 親が無理なく関われる、子どものやる気を引き出すコツ
- ✅ 教育費に備えるための、NISAや保険の見直し
- ✅ 子どもが“自分から学ぶ力”を育てるための環境づくり
など、「家計にやさしく、でもしっかり学べる」方法を発信しています。
「教育にはお金がかかる」
これはもう、間違いのない現実。
でも、限られた予算の中でも、工夫しながら、ちゃんと子どもたちの未来を応援することはできる。
そう信じて、私自身も日々、試行錯誤を重ねながら子育てをしています。
最後に読者のあなたへ
このブログが、あなたの「これでいいんだ」という安心材料になれば嬉しいです。
子育ても、学びも、家計管理も、ひとりで抱え込まずに。