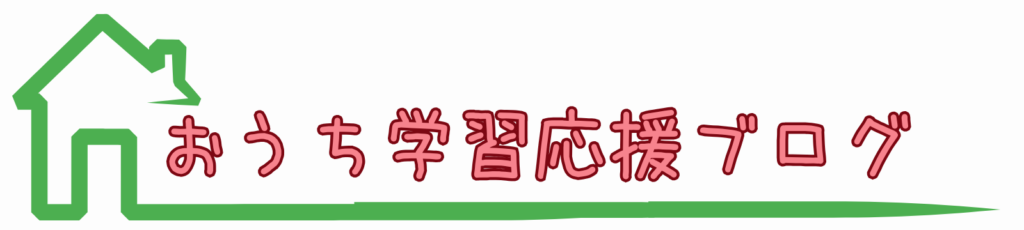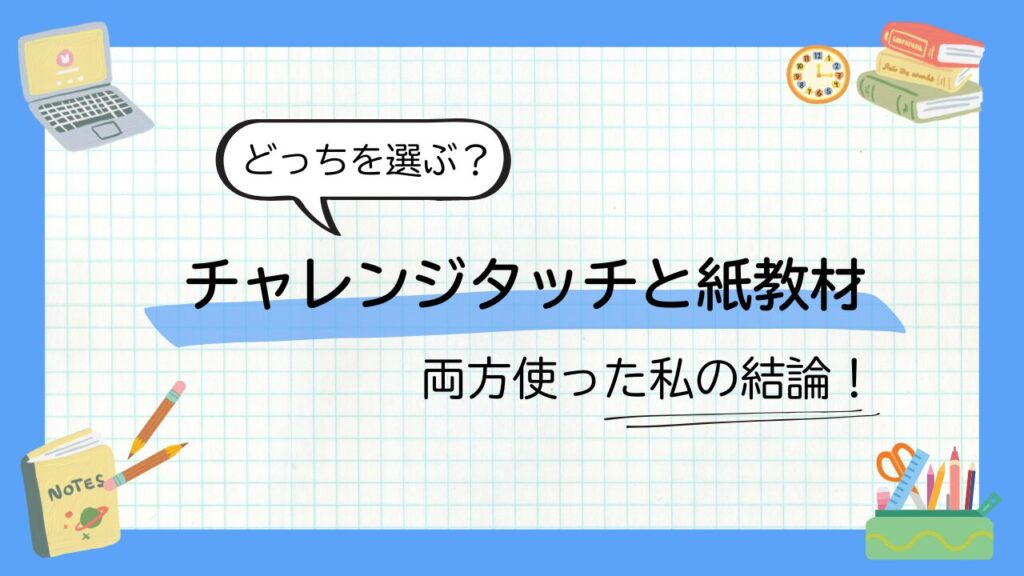進研ゼミのチャレンジタッチ(タブレット教材)とチャレンジ(紙教材)、どっちがいいの?
進研ゼミを検討していると、
- タブレット教材のチャレンジタッチ
- 紙教材のチャレンジ
必ずと言っていいほどどちらがいいのか悩みますよね。



進研ゼミはどちらも魅力的。でも、大切なのは「どちらが合っているか」です。
この記事では、実際に両方を使った我が家の長女と長男の経験をもとに、メリット・デメリットをリアルに解説!
この記事を読めば、お子さんにピッタリな学習スタイルが見つかり、「これで決まり!」とスッキリできるはずなので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
我が家の進研ゼミ活用歴
まずは、我が家の長女(現在5年生)と長男(現在1年生)がどのように進研ゼミを使ってきたのかをご紹介します。
| 低学年(1〜2年生) | 中学年(3〜4年生) | 高学年(5年生〜) | |
|---|---|---|---|
| 長女 | 1年生はチャレンジタッチ → 2年生から紙教材へ変更 | 紙教材を継続。 3年生から自分で丸付けができるように | 自分で学習計画を立て、丸付けまで完結 |
| 長男 | 年長からチャレンジタッチを継続中 | (まだ低学年のため今後の変化に注目) | (未定) |
長女は「タッチペンより鉛筆が書きやすい」と感じて紙教材へ移行。
一方、長男は「ゲーム感覚で楽しく学べる」ことが魅力でチャレンジタッチを継続しています。
長女のケース:チャレンジタッチから紙教材へ
では、進研ゼミに取り組む長女と長男の様子から、チャレンジタッチと紙教材のメリット・デメリットを深堀していきます。
1年生:チャレンジタッチを選んだ理由
長女が1年生のとき、我が家はチャレンジタッチを選びました。
最大の理由は、
私がフルタイムで働いており、親が丸付けをする時間を確保するのが難しかったからです。
また、長女自身も「自分だけのタブレットがもらえる!」というワクワク感から、最初はとても意欲的でした。
実際に使ってみると、
- 自動採点機能で親の負担が大幅に軽減
- 動画解説がわかりやすく、苦手な問題も理解しやすい
- 楽しく学べる仕組みがあり、やる気を持続しやすい
と、メリットがたくさんありました。



長女の場合、最初は良かったのですが、やがて「タッチペンの書き心地が悪く、思うように書けない」というストレスを感じるようになりました。
2年生から紙教材へ変更した理由
「ちゃんと書きたいのに、タブレットだと思ったように書けない…」
長女はこのストレスを解消するため、2年生から紙教材へ切り替えることを決断しました。
すると、
- 書くことへのストレスがなくなり、学習がスムーズに
- シールを貼るご褒美システムでモチベーションアップ
- 書くことで覚える力がついた
といった変化がありました。
例えば漢字練習は、タブレットよりも紙教材の方が書く回数が増えます。
タブレットを使っていた時、長女は、タッチペンの書き心地にストレスを感じて漢字を覚えるどころではありませんでした。



唯一のデメリットは「親の丸付けが必要になること」でした。
でも、3年生になると自分で丸付けができる仕組みだったので、途中から丸付けの負担はなくなりました。
6年生の今|完全に自立した学習スタイルへ
現在、長女は学習計画を立てるところから丸付けまで、すべて自分で行っています。
とはいえ、チャレンジの場合は、
「何日に〇ページをやる」という具体的な学習計画をすでに立ててくれています。
学習カレンダーが付属でついており、やったらシールが貼れる仕組み。
長女は、このカレンダー通りに進めるというめあてを立てて取り組んでいます。
6年生の学習は1日20分~40分ほどで終わります。



紙教材は、自分で学習計画を立てて取り組む力が付きそうだね。



最初は楽しく始められるタブレット学習、学年が上がったら自分で丸付けしたり計画を立てたりできる紙教材にするのは、成長過程に合っていておすすめですよ。
さらに、チャレンジタッチのタブレットは返却不要です。
限られた範囲ではありますが、長女は今でもチャレンジタッチのタブレットを活用しています。
- 学びライブラリーで読書
- AI国語算数トレーニングを活用して、苦手克服や予習
- チャレンジイングリッシュ・オンラインスピーキングに活用して英語学習
ちなみに、チャレンジタッチを退会した場合も、タブレットは活用できます!
長男のケース:チャレンジタッチを継続
長男は年長からチャレンジタッチを始め、現在も継続中。
長男は2年生になりますが、チャレンジタッチがいいそうです。
チャレンジタッチの「楽しさ」が学習習慣につながる!
長男が「チャレンジタッチがいい」という理由の一番は、「楽しいから」。
長男は勉強よりも遊びたい年齢。
でも、チャレンジタッチには、
ルーレットやミニゲーム、お宝集めなどの仕掛けがあるので、「毎日やらなきゃ!」という気持ちになるようです。
「タッチで勉強やらなきゃ今週のミニゲームができないんだよ」と学習をやるきっかけになっています。



低学年のうちは、勉強に対するハードルが低い方が意欲的に取り組めるので、教員目線で見ても良い仕掛けだと思います。



でも、ミニゲームとかがしたいせいで、勉強が雑になっちゃうのは困るな。
チャレンジタッチには、間違えた問題は強制的に解き直しをさせる仕組みがあります。
このおかげで、「早く終わらせたいから適当に解く」という行動を防ぐことができています。
長男はしばらく、チャレンジタッチを続けると思います。
長男はどうしても遊びが優先になってしまうタイプなので、チャレンジタッチの遊びを交えながら学習に取り組める仕組みが必要だと感じているからです。



1年ごとに本人と相談して、紙教材をやりたいと言い出したら変更しようと思っています。
結論!子どもの性格に合わせて選ぼう!
| チャレンジタッチ | チャレンジ | |
|---|---|---|
| 学習スタイル | タブレット学習 | 紙教材による学習 |
| おすすめの年齢 | 低学年向け | 中学年以上 |
| 親の関与度 | 低め(自動採点・動画解説あり) | 高め(丸付けが必要) ただし3年生以降は徐々に丸付け不要になる |
| こんな子におすすめ | タブレット学習が好き ゲーム感覚で学ぶのが好き | タッチペンより鉛筆の方がいい シールを集めるのが好き |
「どちらが良い?」ではなく、「うちの子に合うのはどっち?」と考えることが大切です。
我が家の長女のように、一度やってみて、途中で学習スタイルを変更することも可能です。
長女は、チャレンジタッチをやっていて途中でやる気を失ってしまいましたが、紙教材に変更したことで、またやる気を出して取り組むことができました。
そんな長女の詳しい話はこちら
迷ったら無料体験!まずは試してみよう
「うちの子にはどっちが合うの?」と迷っているなら、試してみるのが一番!
進研ゼミでは、無料の体験教材と資料請求ができます。
- 実際の教材を試せるので、お子さんの反応を見て判断できる
- チャレンジタッチの操作感や、紙教材の使いやすさを事前にチェック
- 申し込み後、数日で自宅に届くので、すぐに試せる
「やってみたら意外と楽しく続けられた!」ということもあるので、まずは気軽に試してみましょう!